Seminar
ゼミのプログラムについて(計4回開催)
福岡会場でのリアル開催とオンラインによる配信を実施しました
第1回

工芸みらいプロジェクト
COTOBA 所長
石井 元 氏
GX対応と持続可能なものづくり
顧客の新ニーズ「エシカル消費」を捉えた企業戦略
デザイン思考による顧客視点(世の中のトレンド)のサービス・ものづくりと、事例として2022年度注目のGX※について学ぶ
※Green Transformation(脱炭素を通じた社会変革)
今年度、経済産業省が設立したGXリーグなど、国際的なカーボンニュートラル実現に向けた流れを理解しつつ、その対応を一つの成長のチャンスと捉える動きが進んでいます。こうした企業の新たな動きと消費者の「エシカル」ニーズを踏まえて今後の経営をどのようにデザインすべきか学びます。
開催日時:2022年9月28日(水)13:00〜17:00
(セミナー + ワークショップを実施)


第2回
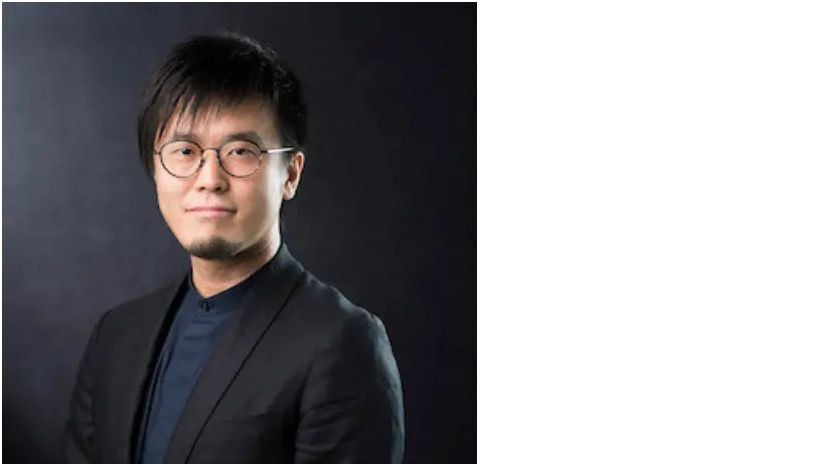
公益社団法人
日本インダストリアル
デザイン協会 理事長
株式会社NOSIGNER 代表
太刀川 英輔 氏
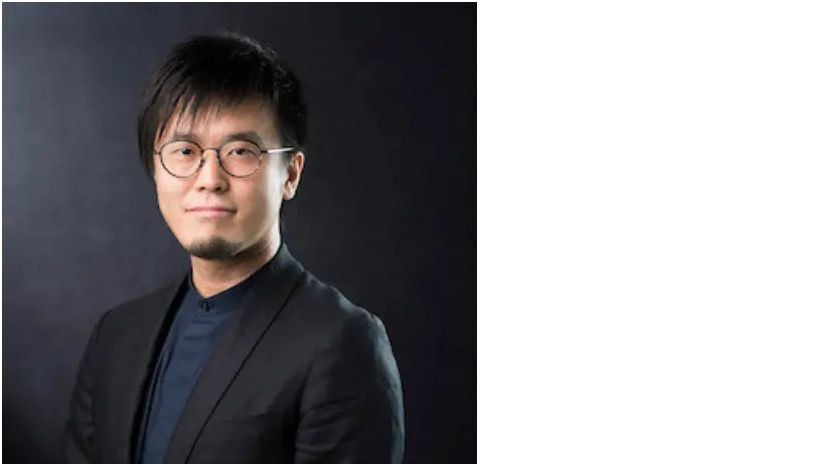
「進化思考」で次の商品を考える
変化を生き残るコンセプトをつくるには?
生物の進化のように変異と適応をくりかえす。変化の時代に生き残るためのコンセプトを生む方法を学ぶ「進化思考」。生物の進化はエラーを生み出す変異の仕組みと自然の選択による適応の仕組みが往復して発生しています。
こうした生物の進化にヒントを得ながら、自社のサービスや商品を進化させていく発想法をワークショップを通じて身につけます。
開催日時:2022年10月21日(金)13:00〜17:00
(セミナー + ワークショップ を実施)


第3回

慶應義塾大学大学院
メディアデザイン研究科 講師
佐藤 千尋 氏

顧客と商品価値を共創する
「技術や価格だけでは売れない」時代のサービスデザイン
企業が商品の価値を作り一方的に販売する時代から、商品を通じて消費者と企業が体験やコミュニティを構築する「サービス主体のものづくり」に近年注目が集まっています。
例えば、オンラインサービスを通じたプレイリスト(楽曲)の共有を目的に利用者同士のコミュニティが発生し、専用プレーヤーが結果的に購入される・・・。こうした、ハードではなくソフトの価値を通じて、利用者と企業が相互に体験を作り出す取組を学びます。
開催日時:2022年11月25日(金)13:00〜17:00
(セミナー + ワークショップ を実施)


第4回

渋谷スクランブル
スクエア株式会社
SHIBUYA QWS
エグゼクティブディレクター
野村 幸雄 氏

都市と地方の連携によるイノベーション
販売連携「都市と地方を結ぶオープンイノベーション」
渋谷から世界へ問いかける、可能性の交差点「SHIBUYA QWS」の運営を通じた地方と都市の共創による新事業創造とコラボレーションについて事例を紹介します。
地域課題解決として企業が「支援する」だけで無く、提供するサービスや商品がSDGsの「誰一人として取り残さない」のコンセプトに合致してるか実証するために活用するなど新たな関係性が見えてきています。こうした持続可能なコラボレーションのあり方を実例を紹介しながら学びます。
開催日時:2023年1月20日(金)13:00〜17:00
(セミナー + ワークショップ を実施)



オークツ株式会社 代表
慶應義塾大学大学院
メディアデザイン研究科
研究員 大江 貴志 氏
九州デザイン経営ゼミコーディネーター
ゼミ全体のファシリテーターを務めると共に、慶應義塾大学メディアデザイン研究科 岸博幸研究室の「地域みらいプロジェクト」メンバーとも連携して、参加者のサービスデザインおよび連携の支援を行います。
大江 貴志 氏 略歴
アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア)にて販売促進や顧客戦略を担当後、ソニーのIT部門に入社し、製版物流の戦略を担当。独立後は大手企業の新規事業開発やネット戦略を行う。慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科創設時に社会人として入学し、初代首席で修了。現在は同大学院の研究員として次世代産業の研究を行いつつ、地域活性に特化した事業をソーシャルベンチャーとしてスピンオフさせてオークツ株式会社を創業。全国で産学官金プロジェクトを企画・実施中。

地域みらいプロジェクトについて
温故知新を合言葉に地域活性を産学官連携を通じて支援
慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科(KMD)岸博幸研究室が取り組む地域活性のプロジェクト。オークツ株式会社は岸研究室の地域活性メンバーが主体となり設立した地域活性のソーシャルベンチャーで、地域みらいプロジェクト事務局を務めています。
詳しくはこちらをご覧ください
地域みらいプロジェクト公式ホームページ